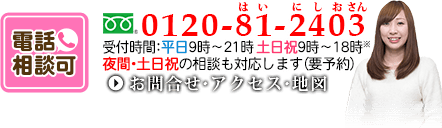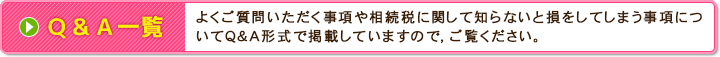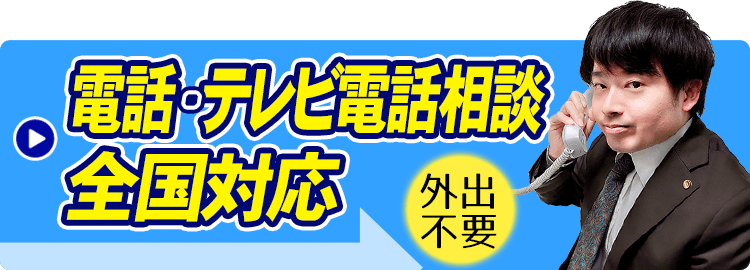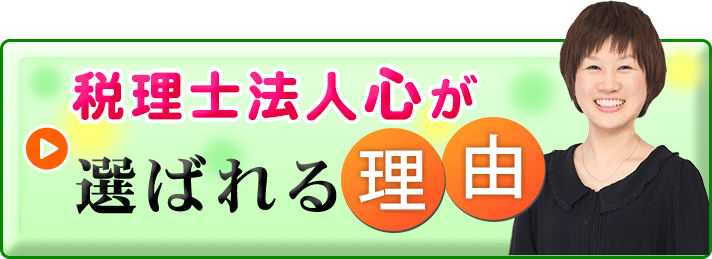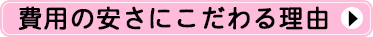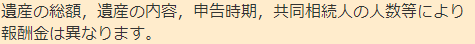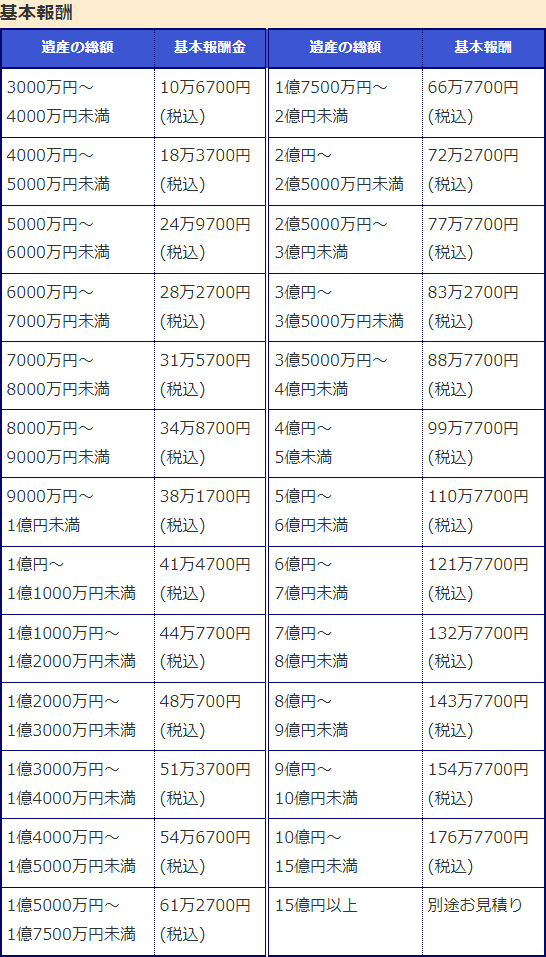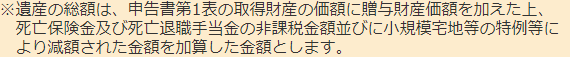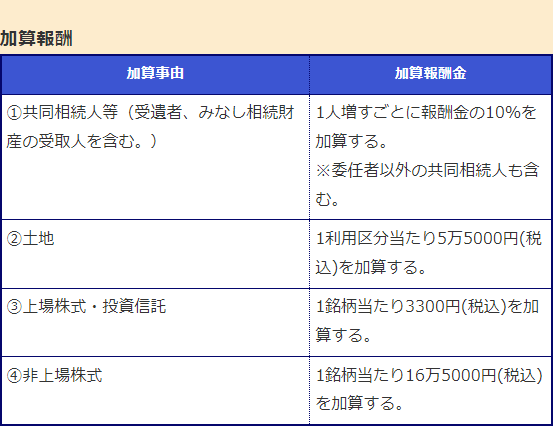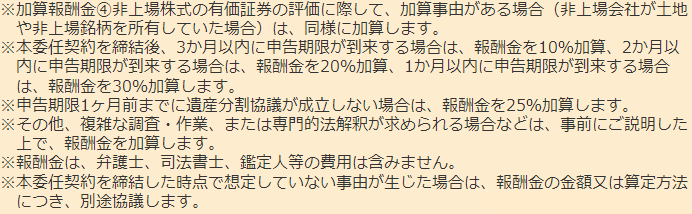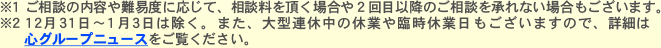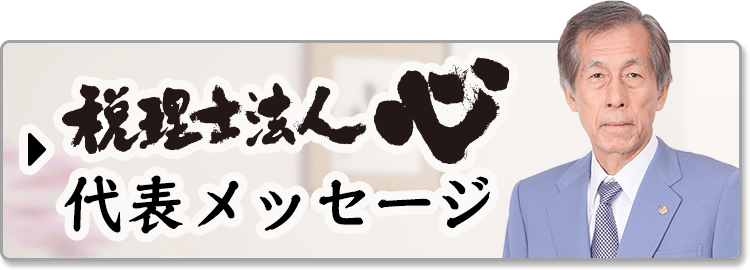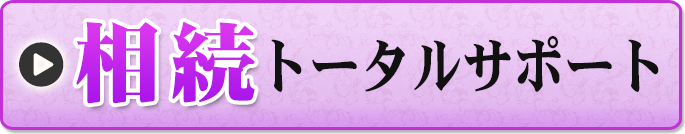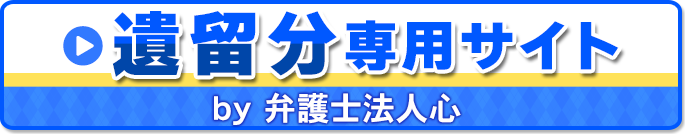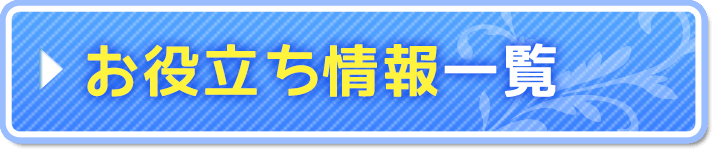お役立ち情報
相続税の路線価を調べる方法
1 路線価の調べ方
相続税の路線価を調べるためには、国税庁がウェブサイトで提供している路線価図を参照します。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書路線価図・評価倍率表
路線価図は、路線価が定められた土地の評価をする際の基本となります。
路線価は1㎡あたりの土地の価格ですので、相続税申告の際の土地の評価においては、路線価に土地の面積を掛けて、様々な補正等をして最終的な評価額を算定します。
以下、路線価図をもとにした土地の評価について詳しく説明します。
2 路線価図は毎年更新される
路線価図は毎年更新され、国税庁のウェブサイトには各年度の路線価が掲載されています。
相続税申告の際の土地評価に用いる路線価図は、相続が発生した年の路線価図です。
仮に被相続人の方がある年の10月にお亡くなりになり、翌年の4月に相続税申告をする場合には、被相続人がお亡くなりになられた年度の路線価を使用します。
3 路線価図に基づく土地の評価
まず、評価の対象となる被相続人の土地の正確な住所地を確認します。
そして国税庁の路線価図のウェブサイトにアクセスし、評価の対象となる土地がある住所地の路線価図を開きます。
路線価図においては、評価の対象となる土地に面した道路の部分に書かれた数字と記号に着目します。
例えば「100D」といった数字と記号が記載されています。
「100」は、その道路に面した土地の1㎡あたりの評価額です。
1000円単位の表記となっておりますので、1㎡あたりの評価額は10万円となります。
なお、Dは借地権割合を示しており、路線価図の欄外に割合が記載されています。
例えば50%と記載されていれば借地権割合は50%ですので、もし土地を貸し付けている場合、借地権割合を控除した金額が評価額になります。
もし、評価の対象となる土地の面積300㎡であり、貸し付けていない場合には、路線価は3000万円となります。
さらに、土地の形状や接道条件等に応じて、補正計算を行って最終的な評価額を計算します。
配偶者に対する相続税額の軽減 相続税の課税の対象とならない財産